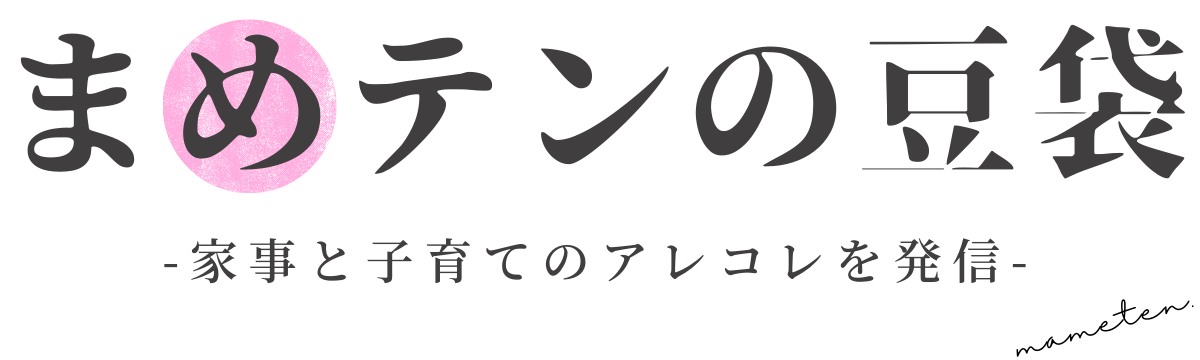秋の気配を感じるイベント、十五夜。
ところで、十五夜ってどんな行事かきちんと知っていますか?
知っているようであまり知られていない、
十五夜についてご説明します!
十五夜にお供えをする意味は?
そもそも十五夜とは何でしょう。
旧暦8月15日の夜にお月見団子を作り、
サトイモ、お酒、ススキ、果物などを月下へお供えすることです。
ご先祖様とのつながり
農作物の収穫
ものごとの結実
これらを連想、感謝をし、お祈りするようになったのが十五夜といわれています。
お供え物は五穀豊穣を願うためだったんですね。
十五夜のお団子の飾り方は?せっかくだから知っておこう!
さて、十五夜と言えばメインはお団子です。
とても簡単にできるので手作りするといいですよ。
(後半で簡単レシピをご紹介します^^)
お団子の準備ができたら飾りつけです!
盛り付ける器
本来は『三方(三方)』という、折敷に台がついたお供え用の器に、
白い紙を敷いてお供えをします。
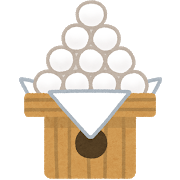
しかし、三方なんてお持ちの方は少ないですよね。
でも大丈夫です!わざわざ、三方を用意する必要はありません!
お盆やお皿を器として使用し、てんぷらの敷き紙などを敷きましょう。
紙の敷き方は下記の通りです。
紙が長方形の場合
四辺または二辺に垂らす
紙が正方形の場合
紙を対角になるように敷いて、端を垂らす
器ができたら、早速お団子を盛り付けましょう!
盛り付け方
1段目
9個 3×3
2段目
4個 2×2
3段目
2個
全部で15個重ねます。
十五夜にちなんで15個なんです!
お供えの位置
盛り付けが完了したら、お供えする位置を決めましょう。
お供えする位置も、実は決まっています。
お月様がみえるところ、または床の間へお供えをします。
お供えした月見団子は縁起物なので必ず食べてくださいね!
「そのまま食べるのは、ちょっと飽きるし多いわ・・・」
そう感じる場合は、アレンジして食べましょう。
みたらし風にしてみたり、あんこをのせて食べたり・・・
これなら、お子さんも一緒に楽しめますよね!
十五夜のお団子の作り方

我が家で毎年作っている、お団子のレシピを簡単に説明します!
上新粉 150g
グラニュー糖 大さじ1
お湯 130ml
【つくりかた】
①耐熱ボールに上新粉、グラニュー糖を入れます。
ゴムベラで混ぜまがら、少しずつお湯を加えていきます。
※このとき、ダマにならないように注意!
②粗熱がとれるまで少し冷まします。
③手で触れるくらいになったら、2分ほどこねてまとめます。
耳たぶくらいの柔らかさになるよう、お湯の量で調整します。
④15等分に分けて丸めていきましょう。
⑤お鍋にお湯を沸かします。(分量外)
沸騰したら、丸めたお団子を入れていき、
お鍋の底につかないよう菜ばしなどで上下に混ぜながらゆでていきます。
⑥茹でている間に、ボウルに氷水をつくっておきます。
⑦お団子を15分ほど茹でたら、氷水の中へ入れます。
⑧バット(またはお皿)にキッチンペーパーをひき、網をのせます。
冷やしたお団子を網の上にのせ、うちわなどで扇ぎます。
こうすることでお団子に照りが出るんです。
以上でお月見だんごの完成です!
こねて茹でるだけなので簡単にできますよ^^
粘土みたいで喜ぶので、子供と一緒に作るのもおススメです♪
お団子だけじゃない!お月見でお供えする野菜と果物
お月見団子についていろいろとご説明しましたが、
実はお月見はお団子だけがお供え物ではないんです。
お月見団子
白く丸い月見団子は満月は、満月に見立てています。
収穫への祈りや感謝はもちろん、
ものごとの結実や健康・幸福をあらわしています。
〈野菜〉サトイモ・さつまいも〈果物〉ぶどう
お月見の時期に採れる野菜や果物をお供えします。
こちらも、収穫への感謝を意味します。
ぶどうにはツルがあるので、お月様との繋がりが強くなるという意味もあります。
ススキ
こちらは野菜、果物ではない植物となりますが
お供えすることによって、魔除けのちからがある
と古くから信じられてきました。
ススキを供えるとこの1年間病気をしない
という言い伝えもあるそうです。
最後に
今ではお月様を楽しむ日、というイメージの十五夜ですが
昔からの色んな思いが込められたイベントなんですね。
今年のお月見は、ぜひいろんな意味のあるお供え物をし、
普段豊かに暮らせていることに感謝、そして1年の健康と幸福を祈って、
お子さんと楽しい十五夜をお迎えください。