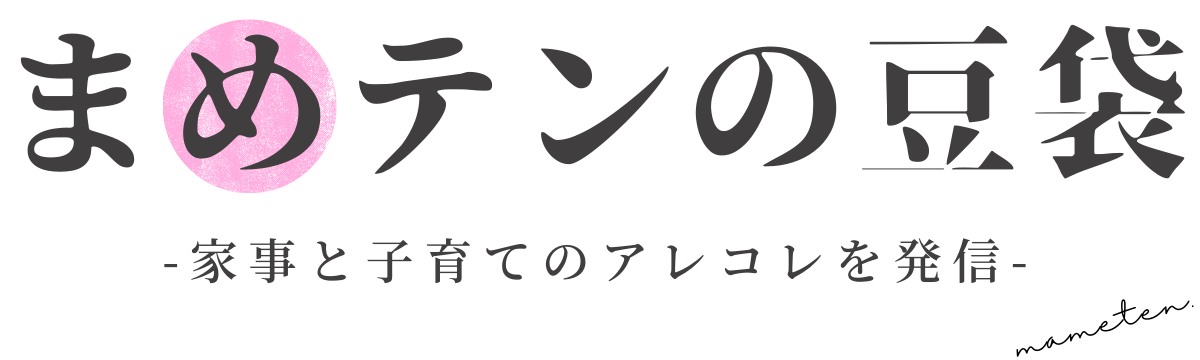お正月といえば何といってもお年玉。
子どもにとっては楽しみでしょうがない一大イベントですが、お年玉をあげる大人にとっては悩ましいものですよね。
ここでは、お年玉事情で一番気になる金額についてまとめました。
・お年玉の年齢別の相場
・金額を一律にするという方法
・子供の人数が違う場合
などの考え方についてご紹介します。
お年玉の年齢による相場はどのくらい?
お年玉はいったいいくらくらいが妥当なんだろう?
毎年準備しながら悩んでいませんか?
あげる間柄によっても変わるものでしょうが、一般的にどのくらいの額を包んでいるのかまとめました。
お年玉を渡す年齢についてはこちらを参考にどうぞ

未就学…500~1000円
小学生…1000円~3000円
中学生…3000円(~5000円)
高校生…5000円(~10000円)
それ以上…10000円
幼稚園児以下の子は、まだお金がピンとこない場合が多いので、ポチ袋とは別にお菓子を渡すととても喜んでくれます。
ガチャガチャができるようにと100円玉5枚などであげても喜びますよ。
小学生は、低学年と高学年で区切って増額して渡す人も多いです。
1~3年生は2000円、4~6年生は3000円などですね。
中高生でも、10000円を渡すのは祖父母からの場合などでした。
甥っ子姪っ子だと、5000円を上限の目安としている人がほとんどです。
大学生、社会人に対しては渡すかどうかも意見が分かれるところですが、渡す場合は一万円が上限という相場でした。
お年玉を入れるポチ袋に関してはこちらの記事をどうぞ(^^)

お年玉の金額を一律にしてもいいの?
親戚の人数が多かったり、行き来が頻繁でお年玉を渡す人数が多いご家族の場合、
「お年玉は一律◯◯円」
と決めているケースもけっこう見られます。
私の旦那さん方の親戚がまさにそうだったのですが、親が6人兄弟で、それぞれの子どもがどこも3〜4人いました。
お年玉をあげる対象は20人ということで、それぞれに相場額をあげていたら家計がパンクする…!
ということで、おじおばからのお年玉は最初から最後まで一律1000円だったそう。
相場と比較すると一人の額は少なめですが、親戚の人数が多ければ集まる額も多いので合わせると大きな額になったりします。
どの子も同じ額なので子ども同士の不公平感もなし。
あの子いくつだったかしら?いくらにする?とならないので、用意する側としても悩まず楽です。
お正月に集まる親戚の人数が多い場合は、お年玉のルールを事前に決めておくといいですよ。
お年玉の金額はあげる人数で変える?
もう一つ、お年玉を用意していて悩ましいのが子どもの人数が違う場合の金額の決め方ですね。
うちは小中学生3人だけど旦那さんの妹のところは園児一人っ子。
こっちは3人にそれぞれ妥当な額をもらったけど、あちらに相場で渡すと、総額で負担を大きくさせてしまう…。
などと悩むことありますよね。
これも本当に難しくて、お金が絡むのでデリケートですし、兄弟間でも相談しづらいことです。
ですが、こう考えてはどうでしょう。
そもそもお年玉というのは、新年のご挨拶にきた子どもに、大人が気持ちとして渡すものです。
本来は親同士の金銭のやり取りではないので、損得勘定を考えなくてもいいものなのです。
子どもの人数で額を考慮していると、子ども同士で金額を確認しあって不公平感が出てしまったり、相手の子どもの人数が増えた時には、上の子へのお年玉は去年よりも減額するの?となってしまったり。
お互い気を遣い合って増額が止まらなくなったり…と色々と面倒なことになります。
十数年間は毎年続くものなので、思い切って相場額にするのか一律にするのかを最初に決めてしまい、お年玉はそういうもの、と割り切って渡しましょう。
どうしても大人の事情が気になる場合、こちらが人数が多い場合は子どもには妥当な額をお年玉として渡し、親へはお年賀としてお土産を渡すなどして気持ちを伝えてはどうでしょう。
こちらが子どもが少ない、またはいない場合はお正月のみのイベント費と考えて割り切り、どうしても負担がきつければ相場より少なめで渡してもいいと思います。
こればかりは絶対に平等にはならない問題なので、大人同士の金銭事情と子どものお年玉は切り離して考える方がスマートだと思います。
まとめ
せっかくの楽しいお年玉。
大事な親戚の子に喜んでもらうものなので、渡す方としても気持ちよく渡してあげたいですね。
大人同士で事前によく確認しあって、できることならお年玉のルールを決めてしまうのがおススメです。
年末年始の大きな杞憂が減りますよ!
気持ちのよいお正月を迎えてくださいね(^^)